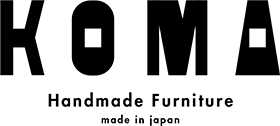Diary
久田拓のスツール

若い衆達が自由に作った作品を会社が買い取って販売する「若い衆作品」という制度がある。
それらを若い衆が発表し俺が批評する場を設けてかれこれ7、8年が経ち、そうやって毎月生まれてくる作品の中から特に優秀なものを製品化してKOMAのラインナップに加えている。
しかし製品化に求められる要素は数多くありそして厳しい。
まず用途を叶えるためのフォルムや掛けた手間に相応する価値が表現できているか、製造工程まで考えデザインした上でオリジナリティがあるか、そして作者の意思を感じることができるか、などなどだ。
若い衆作品から生まれた製品は今のところまだまだ小物ばかりだが、これからのみんなの活躍が楽しみだ。
さて今回の久田拓のスツールだが、今までの若い衆作品の中で最も優れていると評価している。
試作を繰り返す中で、脚の開きの角度の修正を何度も行なっていた。
角度を閉じすぎるとスタッキングした時の重なりが浅くなり、逆に広げすぎると強度的な問題に加え足の小指をぶつけやすくなってしまう。
そして、スタッキングした時に下のスツールの座面と上に重なるスツールの台輪との半端な隙間を嫌い、ちょうど綺麗に重なる位置にもこだわっていた。
そうやって部材一つ一つのサイズや面の形状など全ての工程で最良の選択をしながら、フォルムだけでなく制作工程や製造本数、価格帯まで理にかなったデザインをしていく。
「そうなってしまった」のか「あえてそうした」のか
その制作物の全ての部材や角度、あらゆるフォルムに至るまで必ず「あえてそうした」という作り手の意思が正確に伝わらなければならない。
そのこだわりが人に伝わる物こそ秀作であり、人に伝わらない無意味な意思から生まれた物などいつだって駄作である。
ものづくりは言語を超えたコミュニケーションができる。
作り手の意思が伝わる良い物を目にした時、たとえ言葉が通じなくても互いに笑顔で称え認め合える。
そこには国籍や性別、年齢や立場も何も関係ない。
今回の久田が作ったこのkapo stoolは、言い訳をせず黙々と目標に向かっていく彼の人柄がよく伝わってくる秀作だ。
普通だったら面倒だと敬遠するような工程を楽しみ工夫しながら何度も挑戦した跡が随所に見える。
彼が正月に発表した2025年の目標は「座る道具を毎月1脚つくる」ことだ。
だから毎月の作品発表がすごく楽しみなのだ。
We have "young craftsmen's works" category at KOMA. We pay the craftsmen for the price of the piece and sell them at our shops.
For over 7 years, I have been commenting on the pieces our craftsmen present every months, and some of the exceptional ones have made it into KOMA's products.
But there are lots of severe requirements those pieces has to meet.
Are the shapes fulfilling the purpose of the piece? Is it fully expressing the values that it took to make? Was it designed with production process in mind, but still have originality? Is the designers intention coming through?
At the moment, the pieces that have joined KOMA's lineup are all small items, but I'm looking forward to everyone's challenges in the future.
So I recognize this new stool by Taku Hisada as the most excellent piece of all.
He was making numerous adjustments to the angle of the legs on the way.
When the angle is sharp, stools don't fully stack, and on the other hand when it is in obtuse angle, there are not enough strength and also easy to bump your little finger of your foot.
Hisada was particular about the way it stacks and made sure that there were no space in between seats.
He decided on sizing and shape of the surface as he went on, and designed with not only the form in mind, but the process, volumes and pricing of the product too.
"Did it naturally become this way?" or "Did you intend to make it this way?"
Every material, every angle, every form has to convey the designers intention.
Pieces that convey those attention to details are the masterpieces, and others are just crap.
Craftsmanship is a way of communication without words.
When you see a piece with the designers intention, you don't need words to praise one another. Nationality, age, status, nothing matters.
kapo stool is an excellent piece that expresses Hisada's personality. He always works steadily towards the goal without making excuses.
I notice many challenges that most people would have felt tedious, but he tried over and over again enjoying the process.
Hisada's goal for 2025 is "making one new seating tool a month"
So I'm looking forward to the presentation in the coming months.
Written by Shigeki Matsuoka